こんにちは、souです。
今回は、北野唯我さんが書かれた『内定者への手紙「仕事が遅い人」と呼ばれないための、10のチェックリスト』について解説していきます。
著者の北野さんは、博報堂へ入社し、経営企画局・経理財務局で勤務。
その後、ボストンコンサルティンググループを経て、2016年、ワンキャリアの執行役員に就任した凄腕サラリーマンです。
本書は、そんな著者が、内定者に対して「これをやれば、1年目からぶち抜いた存在になれるよ」ということを詰めた一冊になっています。
これから就職する人はもちろん、20代前半の社会人にも大事なことが書かれていたので、ぜひ参考にしてください。
目次
「いい会社に入りたい」は間違い
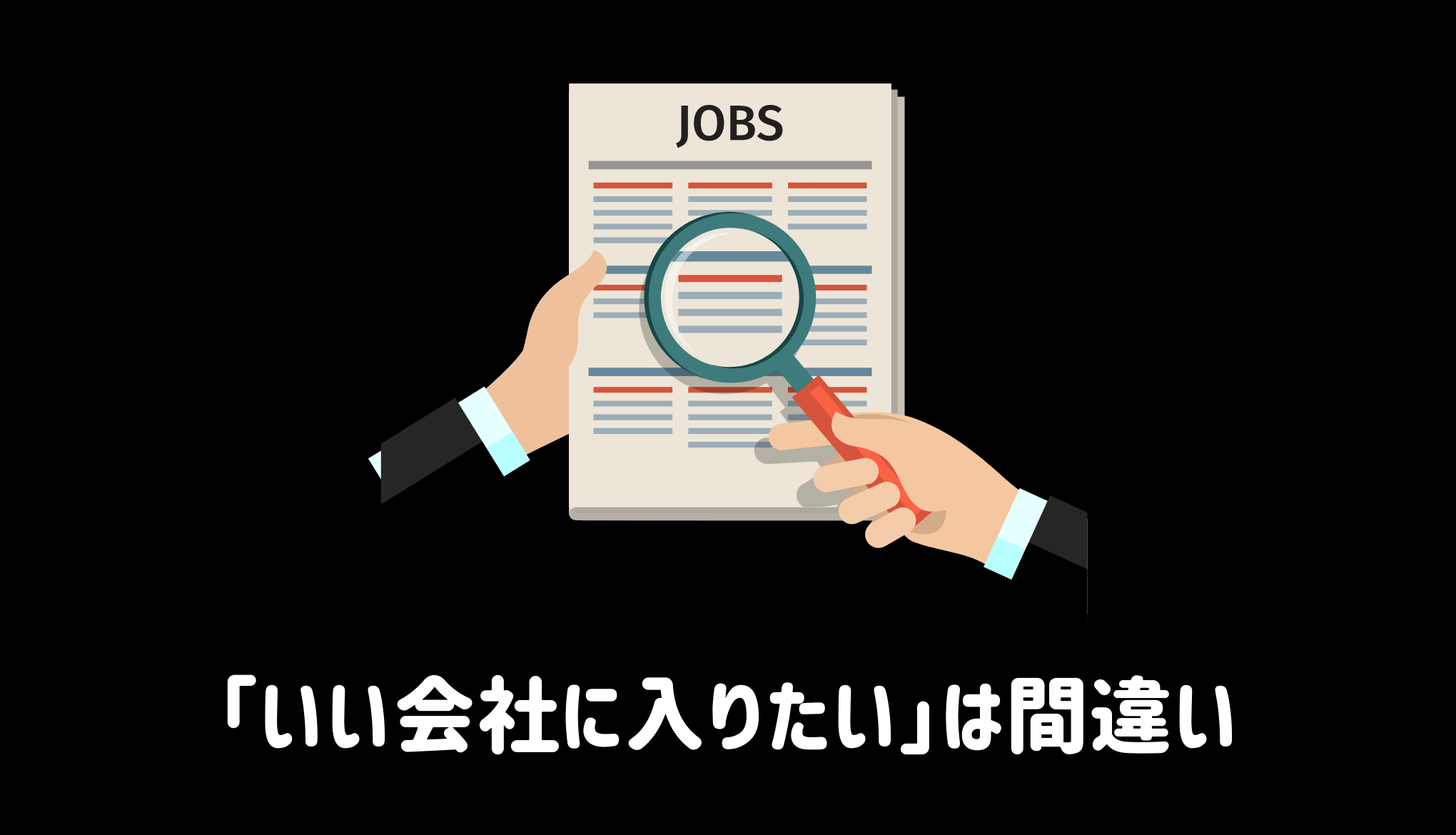
具体的な方法論の前に、大事なことについて触れておきます。
それが、「いい会社に入りたい」は間違いということです。
 まる君
まる君
 まる君
まる君
世の中の働く人が勘違いしていることの1つが、「いい会社や良い環境は与えられるものではない」ということ。
確かに、学生時代までは環境は与えられますよね。
ただ、働き出したら、事業の一端を担っていることになります。
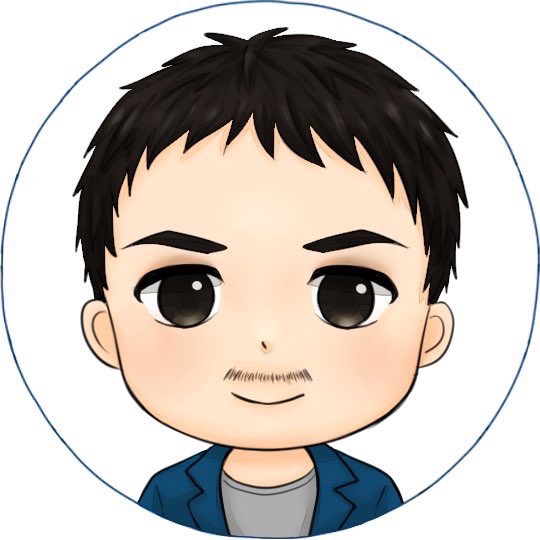 souさん
souさん
確かに、就活していると、「いい会社」には「いい人」が殺到します。
ただ、もっと大事なのは、「もっといい会社」には「もっといい人」が殺到するということです。
そうすれば、結果必ず食べていくことができる。
これは、著者がこの本の中で、繰り返し話していた言葉です。
まずは、この言葉を頭にすり込んでおくのが良さそうですね。
仕事で大事なのは、量でも質でもない

仕事で大事なのは、量か質か?という問題は、いろんなところでされていますよね。
どうでしょう、あなたはどっちが大切だと思いますか?
 まる君
まる君
著者の答えは、「どちらでもない」です。
そして、量と質の代わりに「スピード」を挙げています。
著者いわく、「スピードは、質にも量にも転換させられるから」とのこと。
これは、「確かに!」と納得の部分でした。
ただし、スピードには問題点が2つあります。
②歳を重ねると早ければ早いほどいいわけではなくなる
それぞれの問題点について、解説していきます。
問題点①:ビジネス人生の最初の4〜5年で決定される部分が多い
人間は、習慣に左右される生き物です。
そのため、一度ついたスピードを後から変えるのは難しいのが現状です。
歳をとってから動きが遅くなることはあっても、早くなることはほとんどありません。
つまり、最初の数年間でゆっくりしたスピードで働いてしまうと、そのあと早いスピードに変化するのが難しいということです。
「スピードの基準値は27歳までに決まる」
これを、意識することが大事ですね。
問題点②:歳を重ねると早ければ早いほどいいわけではなくなる
27歳までに早いスピードを身につけることは大切ですが、そのあとは「スピードの幅」を持つことが重要になります。
スピードの幅を持つとは、「毎時全速力で走り続ければいいといいことではなく、27歳を超えたあたりからは、「中速」と「低速」を意識的に使い分けられるようにならないといけない」ということです。
何はともあれ、27歳まではスピードを意識して仕事をすることが大切というわけです。
仕事のスピードを上げる方法
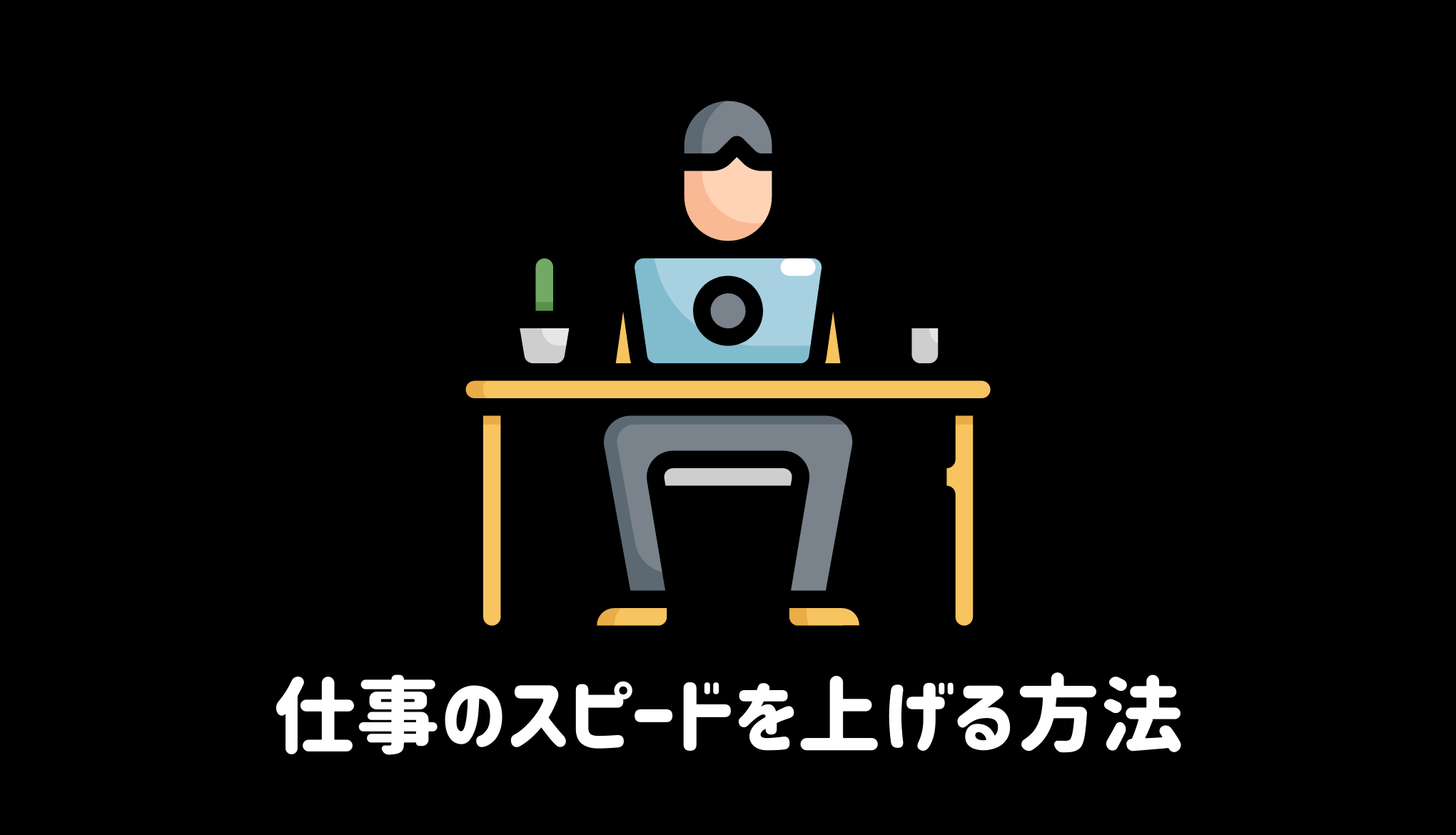
具体的に、仕事のスピードを上げる方法についても触れておきます。
②分解の法則
③計測の法則
この3つの法則を意識することで、仕事のスピードが早くなります。
では、それぞれ見ていきましょう。
①目標の法則
目標の法則とは、「自分で自分の目標を立てる訓練をする」ということです。
職場を見てみると、次のような2つのパターンに分かれますよね。
②いつも遅くまで働いているのに、延々と成果につなげられない人
両者の違いは、どこにあるのでしょうか?
答えは、「自分で目標を立てているか」です。
「あの大学でこれを学びたい」という目標があって、そこから逆算して勉強を始めます。
しかし、仕事になった途端、これができない人がいるのです。
誰かに決められた目標だけをこなしているのは、行きたくもない志望校のためにいやいや勉強している状態です。
これだと、受かる可能性は限りなくゼロに近いですよね。
「目標→プロセス→知識」
成果を効率的に出すためには、この順番で進めることが必須なのです。
②分解の法則
目標を立てられるようになったら、具体的にプロセス自体を効率的に最短でこなす方法を考える必要があります。
ここで役立つのが、「分解の法則」です。
ただ、目標がプラス10kmの「150km」だとしたら、どう分解して考えるべきでしょうか?
『球速=筋力×筋力の出力率×投球フォームの効率性』
正解はないですが、このような分解ができますよね。
こうやって分解することで、次のような仮説を立てることができます。
・それとも、投げるときのフォームを改善すべきなのか?
・はたまた、柔軟性を上げるべきなのか?
仕事において、仮説はとても大事です。
この辺りの話については、【書評】「コンサル1年目が学ぶこと」の要約と感想【圧倒的なビジネスマンになれます】で解説しています。
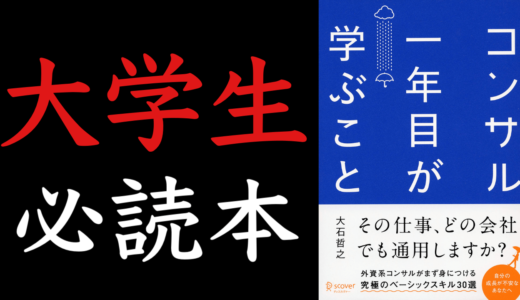 【書評】「コンサル1年目が学ぶこと」の要約と感想【圧倒的なビジネスマンになれます】
【書評】「コンサル1年目が学ぶこと」の要約と感想【圧倒的なビジネスマンになれます】
企画書を1つ作るにしても、細かくみると、10以上のフローが存在しています。
仕事を早くするためには、このフローを分解して考える必要があるわけですね。
③計測の法則
目標と分解ができるようになったら、最後は「計測」しましょう。
勉強でも仕事でも、「数字」は貴重な財産です。
すると、「自分は特に二次関数が弱いんだな」と知ることができますよね。
このように、何をするにも数字を取っておくことは、とても大切なんです。
・エクセルで表を作るのに、どのくらいの時間がかかるか?
・どの仕事にどのくらいの時間を使っているのか?
こういったことをパッと答えられない人は、仕事ができない人である可能性が高いです。
というのも、この状況は、野球のピッチャーが自分の最高球速が何キロか知らない状態だから。これだと、練習のしようがないですよね。
まずは、自分がどの仕事にどのくらいの時間を使っているのか、「計測」することが大切なんです。
まとめ:前夜からの準備が大切
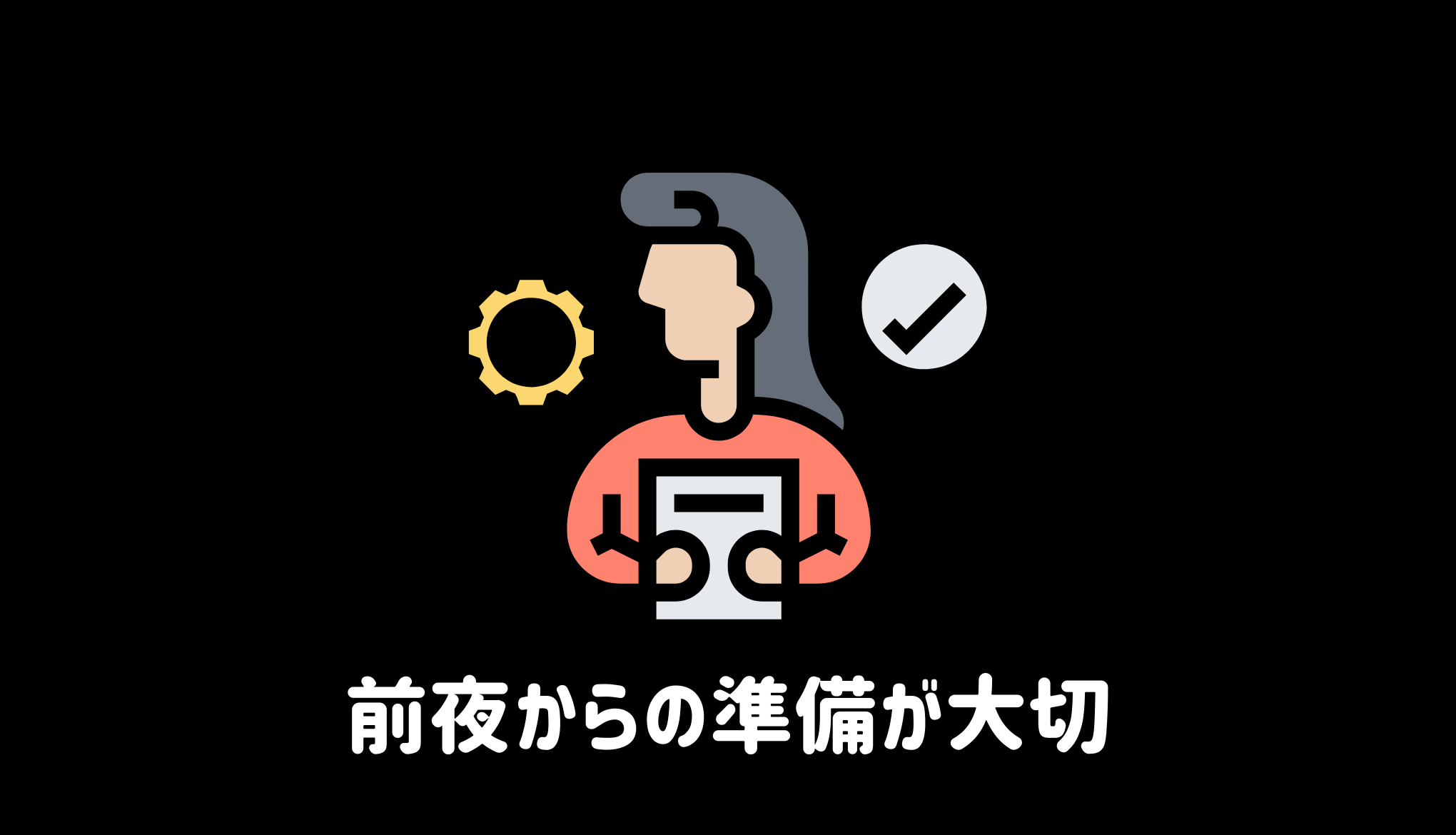
最後に、「できる人は前夜から準備している」という話をします。
確かに、仕事ができる人は、朝のうちに高い集中力を発揮して、重要なタスクをこなしますよね。
ただ、着目すべきは、仕事ができる人たちの前夜の行動です。
優れたビジネスパーソンは、前夜のうちに朝やるタスクに、少なからず取りかかっています。
・それをスケジュールに組み込む
・明日の服やカバンの準備をしておく
具体的には、上記のようなことです。
こういった少しの行動が、次の日の生産性を上げてくれます。
寝る前の行動については、【実証済み】人生を激変させる寝る前10分の使い方でまとめました。
 【実証済み】人生を激変させる寝る前10分の使い方
【実証済み】人生を激変させる寝る前10分の使い方
ぜひこの本を参考に、できるビジネスパーソンへの一歩を踏み出してください。
では、また。

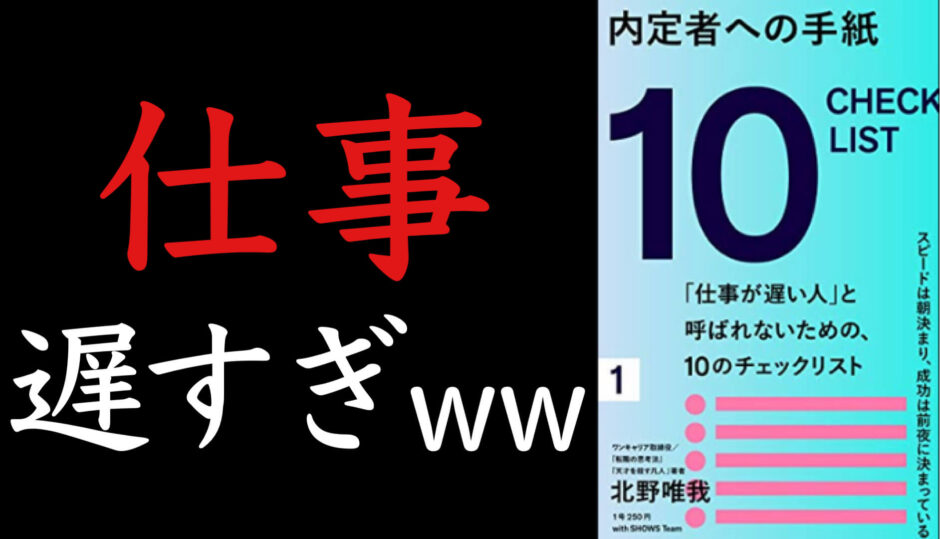

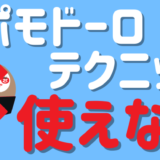
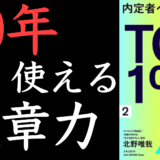
コメントを残す